



M&A(Mergers and Acquisitions:企業の合併・買収)は、経済構造が大きく変化している現代において、成長や事業承継を実現するための重要な手段として位置づけられています。特に日本国内では、中小企業の後継者不足を背景に、M&Aのニーズが年々高まり、M&A業界の市場も急速に拡大しています。
日本企業の大多数を占める中小企業では、経営者の高齢化とともに後継者不足が深刻化しています。帝国データバンクの調査によれば、60代以上の経営者のうち約半数が後継者未定であり、黒字経営にもかかわらず廃業を選択するケースが後を絶ちません。
こうした状況において、第三者への事業承継手段としてのM&Aは、企業存続の鍵を握るソリューションとされているのです。
かつては大企業間の大型M&Aが注目を集めていましたが、近年では地方の中小企業を中心とした「スモールM&A」が増加傾向にあります。これは単なる企業買収ではなく、地域社会の雇用や経済を守る役割も担っており、社会的な意義の高い仕事と見なされています。
また、M&Aアドバイザーやコンサルタントといった職種は、専門性と信頼性が求められる分野である一方、未経験者にも門戸が開かれつつあります。実際に、金融業界や不動産業界、コンサルティングファームからM&A業界へのキャリアチェンジを目指す人が増え、転職市場での注目度も高まっているのが現状です。
政府も中小企業の事業承継を支援する施策を強化しており、M&A業界全体の成長は中長期的にも期待されています。DX(デジタルトランスフォーメーション)やAIなどの技術も活用され始めており、M&Aのプロセス自体も効率化・高度化が進んでいる点も見逃せません。

M&A業界への転職は将来性があり魅力的ですが、誤った理解や準備不足によって思わぬ失敗に陥るケースも少なくありません。ここでは、実際に多くの転職希望者がつまずきやすいポイントと、注意すべき落とし穴について詳しく解説します。
M&A業界=高年収・華やかな業界というイメージを持って転職を希望する人が多く見られます。しかし、実態は非常に地道な努力が求められる世界です。案件獲得から成約に至るまでには長い時間と人間関係構築が必要であり、プレッシャーや責任の大きさも相応に伴います。
「数字さえ出せば評価される」「成約すればそれでいい」という短絡的な考えで入社すると、ミスマッチが起きてしまうことがあるのです。
特に未経験者が見落としがちなのが、ファイナンス知識や法務理解の重要性です。M&A業務では財務諸表の読み取り、企業価値の算定、契約書に関する理解が不可欠であり、学ぶべき範囲は多岐にわたります。
こうした専門性を補う準備なく転職してしまうと、業務についていけず早期離職に至るリスクが高まります。
もう一つ大きな要素が、企業文化との相性です。M&A業界はスピード感と成果主義が強く、営業志向の強い企業が多いのが特徴です。自主性・行動力が重視される反面、指示待ちタイプの人には向いていない可能性があります。
そのため、企業ごとのカルチャーや評価制度を事前に把握し、自分の価値観とのフィットを見極めることが大切です。
たとえば、前職が金融業界だった30代男性が「金融知識を活かせる」としてM&A企業に転職したケースでは、営業スキルや新規開拓に苦労し、半年で退職してしまったという事例があります。
また、逆に営業経験豊富な方が「コミュニケーション能力で勝負できる」として入社したものの、企業分析や契約手続きの煩雑さに対応できず、活躍できなかった例もあります。
M&A業界への転職を成功させるには、正しい理解と入念な準備が欠かせません。この章では、具体的にどのような準備をすればよいか、ポイントごとに詳しく解説していきます。
まずは業界全体の構造やプレイヤーを理解することが重要です。M&A仲介会社、アドバイザリーファーム、FAS、投資銀行など、同じM&A業界でも業態によって業務の中身は大きく異なります。
たとえば、仲介会社では1人の担当者が売り手・買い手両方の支援を行う「両手型」スタイルが一般的ですが、アドバイザリーファームでは「片手型」で、専門性の高いアプローチが求められることが多いです。
同じ仲介型の企業でも、会社の規模や戦略によって求められる人材像は異なります。たとえば、独立系のM&Aブティックは少数精鋭で即戦力が重視される傾向があります。一方で、大手仲介会社は教育体制やサポート体制が整っており、未経験者にも門戸を開いている企業も増えています。
求人票の表面だけで判断せず、OB訪問や企業説明会などで「内情」に触れる努力が必要です。
未経験者がM&A業界で活躍するには、入社前からの基礎知識のインプットが不可欠です。特に重要なのは次の3つです。
財務三表(PL・BS・CF)を読めることは最低限必要です。加えて、企業価値評価(バリュエーション)の考え方や、DCF法、マルチプル法などの知識も徐々に習得していくと良いでしょう。
M&Aの進行には、「案件発掘 → ノンネーム → ネームクリア → LOI提出 → デューデリジェンス → 最終契約 → クロージング」といったフェーズがあります。各段階で何が求められるのかを体系的に学ぶことで、面接でも具体的に話すことができます。
最終契約(SPA)や秘密保持契約(NDA)など、M&Aで交わされる契約書の種類や概要は把握しておくと面接でも差がつきます。法律の専門家になる必要はありませんが、基本的な枠組みを理解しているだけでも業界理解が深まります。
M&A業界では、短期的な成果よりも中長期的な志向が重視される傾向があります。そのため、面接では「なぜM&A業界に進みたいのか」「将来どうなりたいのか」という部分を深掘りされることが多いです。
たとえば次のような要素を盛り込むと良いでしょう。
M&A業界の選考プロセスは他業界と比較して特徴的な点が多く、対策を怠るとチャンスを逃すことにもつながります。ここでは、転職活動を進めるうえで注意すべきポイントを整理し、失敗を防ぐための具体的な行動を紹介します。
「どの会社もM&Aをやっているから似ているだろう」と思い込み、企業研究をおろそかにしてしまうのは大きな落とし穴です。
M&A業界には、以下のようなタイプの企業があります。
| 種類 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 仲介会社 | 売り手と買い手の両方を担当 | 営業力やフットワークに自信がある人 |
| アドバイザリー会社(FA) | 片方の当事者を支援し専門性を発揮 | 分析や交渉に強みを持つ人 |
| コンサルティング会社 | PMIや戦略支援に強み | M&A後の企業統合に興味がある人 |
同じM&Aでも提供する価値や働き方は大きく異なります。自分の適性と志向性を踏まえて、応募先の選定を丁寧に行いましょう。
職務経歴書や履歴書は、第一関門です。M&A業界では「ロジカルな文章力」や「成果の数字化」などが評価されやすいため、書類の内容にも工夫が必要です。
M&A業界の面接では、志望理由と業界理解が両方見られます。表面的な言葉ではなく、自分の経験や価値観とリンクさせて話せるかが評価のカギです。
以下は、よくある質問例と回答の方向性です。
| 質問例 | 回答のポイント |
|---|---|
| なぜM&A業界を志望したのですか? | 過去の経験と業界の役割を結びつける(例:営業職で培ったヒアリング力を活かしたい) |
| なぜこの会社を選んだのですか? | 他社との違い(戦略・組織・文化)を具体的に述べる |
| 入社後に実現したいことは? | 長期的なビジョンと業界への貢献を語る |
面接の最後にある「逆質問」は、自分の理解度と熱意を示すチャンスです。以下のような質問は評価されやすい傾向があります。
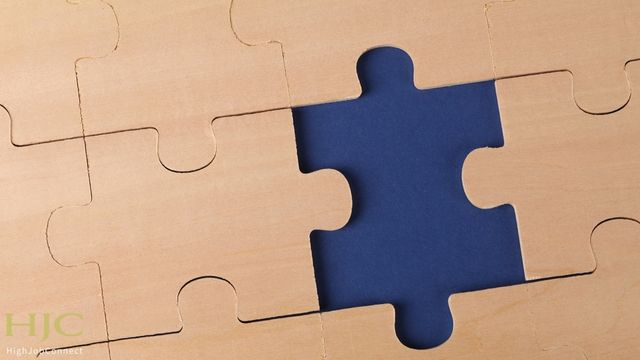
M&A業界は専門性が高く、成果主義的な側面も強いため、実際に働き始めてから「思っていた業務と違う」「想像以上にハードだった」とギャップを感じるケースが少なくありません。転職後のミスマッチを防ぐためには、入社前から情報収集と自己認識をしっかり深めておくことが重要です。
M&A企業によって、カルチャーや価値観、働き方には大きな差があります。特に重要なのが「社風」と「評価制度」です。
たとえば、結果重視型で個人裁量が大きい会社と、チームプレーを重んじる会社では、求められるスタンスが全く異なります。また、インセンティブ制度の有無や評価の透明性も、モチベーションに影響する大きな要因です。
これらを入社前に人事や社員インタビューなどから確認しておくことで、ギャップを最小限に抑えられます。
もう一つの落とし穴は、「業務内容の理解不足」です。
M&A業界では華やかなイメージが先行しがちですが、実際の仕事には泥臭さや事務作業の多さも伴います。資料作成、クライアントとの地道なやり取り、数字の整合性チェックなど、地味な作業も多いのです。
リアルな業務を知ることで、「成約までの道のりの長さ」「関係各所との調整の難しさ」など、入社前に自分の適性と照らし合わせて考えることができます。
自分にとって「ギャップになりそうな部分」はどこか?を把握するために、自己分析が欠かせません。
こうした棚卸しを行った上で、企業の特徴と照らし合わせておくことで、違和感やギャップをあらかじめ想定し、対策を立てることができます。
M&A業界における転職は、他の業界と比べて専門性や即戦力性が重視されるため、失敗しないためには“戦略的な準備”が不可欠です。ここでは、採用担当者に好印象を与え、選考を突破するための実践的な対策法を紹介します。
M&A業界では、職務経歴書の内容が重視されます。フォーマットだけでなく、「何を伝えるか」が問われます。
売上向上率、業務改善の効果、プロジェクトの規模など、できるだけ数値で成果を示すことが重要です。
営業力、分析力、交渉力、ファイナンス知識など、M&Aに直結するスキルは明確に記載しましょう。
異業種からの転職者に特に求められるのが、「なぜM&Aなのか」の説得力。業界への興味や適性、将来像まで言及できると効果的です。
面接では、志望動機やスキルの確認に加えて、「業界に対する理解」と「現場レベルのシミュレーション対応力」も問われます。
を想定した判断力を見る
近年の選考では、簡易的な「M&A案件の仮提案」などのケース問題が出されることもあります。
準備方法としては:
を把握しておくと、面接時の対応力が高まります。
M&A業界の転職では、業界理解が深く、企業側とのリレーションを持っている転職エージェントの存在が鍵になります。
M&A特化のサービスである「ハイジョブ」や「ハイジョブコネクト」などを利用すれば、専門エージェントからのアドバイスが得られ、選考通過率の向上にもつながります。

M&A業界への転職は、やりがいや高年収といった魅力がある一方で、高い専門性や精神的タフさが求められる世界でもあります。だからこそ、転職活動の中で「準備不足」や「理解不足」があると、入社後にギャップを感じてしまうケースが少なくありません。
転職成功のために必要なことは、以下の3点に集約されます。
また、独力での情報収集や準備に不安がある方には、M&A業界に精通した転職エージェントの活用がおすすめです。たとえば「ハイジョブ」や「ハイジョブコネクト」など、M&A特化型の支援サービスを活用すれば、企業ごとの面接傾向や内情まで把握した上でのサポートが受けられるため、内定獲得の確率は飛躍的に高まります。
転職は人生の転機です。だからこそ、確かな準備と戦略をもって臨むことが重要です。あなたのM&A業界への第一歩が、確かなキャリア構築へとつながるよう願っています。