



M&Aは、企業成長や事業承継、再編戦略の中核を担う手段であり、近年では大企業のみならず、中小企業やスタートアップにおいても積極的に活用されるようになりました。
しかし、その一方で、M&Aの増加に伴い、取引の公正性・透明性・安全性を確保するための法規制が年々強化されています。
これまでのように、専門家に任せておけばよいという時代は終わり、M&Aの実務に携わるすべての人が、法的リスクとその対処法を理解しておく必要がある時代に突入しています。
法規制が注目される最大の背景には、経済構造の変化と、M&Aの社会的影響力の拡大があります。
たとえば、大企業によるスタートアップの囲い込み、外資による重要インフラ企業への買収、不透明な買収スキームを巡る株主訴訟の増加など、M&Aはもはや企業内の戦略だけで完結する話ではなくなっています。
これらに対応する形で、独占禁止法や外為法、会社法などの関連法令は、より厳密で実務的な方向へと見直されてきました。
また、デジタル領域の発展に伴う個人情報保護や競争環境の確保など、新たな課題にも対応が求められています。
M&Aの法規制というと、弁護士や法務部門だけの話と捉えがちですが、実際にはアドバイザー、財務担当、投資家、経営者など、あらゆる関係者が影響を受ける対象です。
たとえば、企業結合審査の対象となった場合、情報開示の範囲が広がり、実務担当者の負担が大きくなることもあります。
また、クロージングが予定よりも遅延したり、許認可の取得に関する新たなプロセスが必要になったりと、案件スケジュール全体に及ぼす影響も無視できません。
法規制はリスクであると同時に、正しく理解し活用すれば、競合との差別化やクライアントへの信頼構築にもつながる重要な武器となるのです。
2020年代後半に入り、M&A関連法規は目まぐるしくアップデートされています。
特に2024年〜2025年にかけては、経済安全保障の強化や投資家保護の観点から、各法令での見直しが加速しました。
ここでは、M&A実務に影響を与える代表的な3つの法改正トピックを取り上げ、そのポイントと実務への影響を整理していきます。
公正取引委員会は、2023年末にガイドラインを改正し、企業結合審査における情報開示義務の強化と、審査対象となる取引の範囲拡大を発表しました。
これにより、従来は審査対象外だったスタートアップ買収や、海外法人を経由した合併も、条件によっては日本国内での審査が必要になるケースが増えています。
また、AI・SaaSなどのデジタル分野では、従来の売上基準ではなく、技術力・データの独占性を重視した評価軸が導入されつつあり、企業側にも新たな対応が求められています。
2024年の改正会社法では、株式の取得・交付に関する要件が一部見直され、特定株主への譲渡制限や事後開示義務の強化が盛り込まれました。
特に、敵対的買収やTOB(株式公開買付け)への防衛策が課題となっていた背景を受け、経営陣・株主・投資家それぞれの権利を調整する新ルールが導入されています。
これにより、M&Aスキームの設計段階から、法務部門だけでなくアドバイザーも深く関与する必要が出てきています。
クロージング直前に開示義務が発生することもあるため、契約内容に柔軟性と明確性の両方を求められる時代になっているのです。
経済安全保障を背景に、外資による国内企業の買収に対する規制も強化が続いています。
特に、防衛・エネルギー・インフラなどの「重要事業分野」に属する企業の株式取得については、外為法による事前届出の範囲が拡大されました。
この改正により、外国資本が10%以上の株式を取得する際には、より厳格な審査・承認プロセスを踏む必要があるため、スケジュール調整や法務対応に慎重な計画が求められます。
また、国内企業側も「自社が外為法の対象に該当するか否か」の判断を誤ると、行政指導や案件ストップといった重大なトラブルを招く恐れがあります。
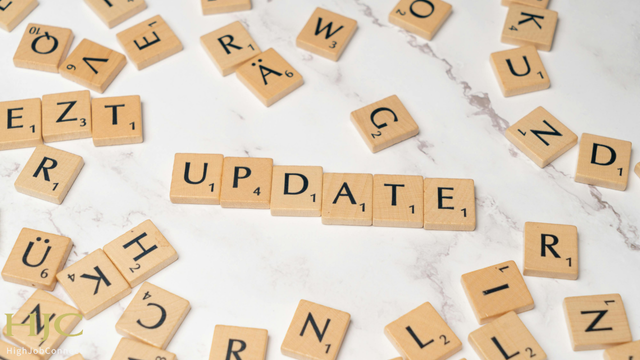
法規制の変化は、単なるルールの話にとどまらず、M&Aの実行可否、スケジュール、リスクマネジメント全体に直結します。
特に、企業の内部体制やM&Aの意思決定プロセスに関わる人々にとって、法改正を正しく把握していないことは、致命的なボトルネックとなりかねません。
ここでは、近年の法改正がどのように現場の実務へ影響を与えているのかを、具体的に紐解いていきます。
独占禁止法や外為法の改正により、事前審査が必要な取引の範囲が拡大しています。
これにより、M&Aの初期段階から法務・経営・アドバイザーが連携し、審査対象の有無、必要な提出書類、開示義務の範囲を確認する作業が必須になりました。
とくに中堅・中小企業の買収であっても、買収先が外資規制の対象業種であったり、グローバル企業との連携がある場合には、無意識にリスクを抱えることになります。
法規制の強化は、クロージング(最終契約締結)までの期間にも影響を及ぼします。
たとえば、企業結合審査や外為法の届出が完了するまで、契約書を締結していても取引を実行できない“サスペンス条項”が挿入されるケースが増加しています。
こうしたプロセスの長期化は、取引相手との信頼関係や、社内の温度感にも影響を与えるため、スケジュール管理と説明責任がこれまで以上に重要になっています。
具体的には、審査完了までに最低○週間を要することを契約前に明示し、関係者全体の理解を得ておくことがリスク回避に直結します。
法改正の影響は、大型ディールに限った話ではありません。
たとえば、譲渡側が個人である中小企業のM&Aでも、買収側の出資者やグループ企業が外資比率の高いファンドだった場合、外為法の届出が必要になるケースがあります。
また、株主構成や従業員情報、財務情報の取り扱いにおいても、個人情報保護や労働法との整合性を考慮しながら進めなければならず、「法務に弱いアドバイザー」が携わると、プロセスが止まることすらあります。
こうした背景から、中小M&Aにおいても法務リスクに精通したアドバイザーや、専門家との連携体制が前提となる時代へと変わりつつあります。
法改正は毎年のように更新され、その都度、M&A実務の進め方にも調整が求められます。
特に2020年代後半の法規制強化は、アドバイザーや企業の法務部門にとって、単なる知識のアップデートでは済まされない“実務的な改革”を意味しています。
では、どのような点に気をつけ、どのような体制を整えておくべきなのでしょうか。
ここでは、現場で役立つ具体的な対応のポイントを解説します。
急速に変化する法規制に社内だけで対応しようとすると、どうしても限界が生まれます。
そこで重要なのが、顧問弁護士・税理士・公認会計士など外部専門家との連携体制です。
たとえば、事前届出が必要か否かの判断や、独占禁止法の適用範囲、買収契約書への条項反映などは、実務経験豊富な士業の意見が不可欠です。
また、重要なステップでのダブルチェックを徹底することで、後から指摘されるミスや、重大な法的瑕疵を未然に防ぐことができます。
社内での法務レビュー体制の強化と、定期的な法改正のキャッチアップを両輪で進めることが、持続可能なM&A実務を支える基盤になります。
近年の法改正を受けて、契約書のドラフトにも変化が出てきています。
たとえば、独占禁止法の審査結果が出るまで効力を停止する“サスペンス条項”や、外為法による拒否権条項などは、今やほぼ標準の記載内容です。
加えて、情報開示義務に関する条項や、レピュテーションリスクを防ぐための秘密保持・再開示制限の強化なども重視されるようになっており、以前よりも高い精度での契約設計が求められています。
契約書は単なる手続きではなく、法的リスクを可視化し、対策を事前に仕込むための“設計図”です。
だからこそ、M&Aアドバイザー自身も契約内容に一定の理解を持ち、士業と連携しながら調整する姿勢が不可欠です。
M&A実務経験者が転職や独立を考える場合、法務知識は大きな強みとなります。
とくに、最近では「法規制に強いM&Aアドバイザー」が企業から高く評価される傾向が強まっており、キャリアアップや年収交渉に直結するポイントとなっています。
また、独立後にフリーランスとして活動する際にも、法務対応の可否はクライアントからの信頼度に直結します。
「契約はすべて弁護士に任せる」という姿勢ではなく、一定の知識を持った上で、リスクの所在や調整ポイントを先回りできるアドバイザーこそ、選ばれる時代になっているのです。

M&Aを取り巻く法規制は、年々複雑化・厳格化の一途をたどっています。
しかしそれは、リスクの増加だけを意味するものではありません。
むしろ、法規制を正しく理解し、実務に落とし込める人材は、これからのM&A市場で高く評価される存在となるのです。
企業結合審査の対象拡大、外資規制の強化、会社法における株式取得の見直しなど、変化の激しい状況においても、情報を常にキャッチアップし、実践に活かせる力が求められています。
特に、転職や独立を視野に入れているM&A実務者にとっては、「法規制に強いこと」が差別化要素であり、武器になる時代です。
だからこそ、今このタイミングで、自身のスキル棚卸しとキャリア戦略を見直すことが大切なのです。