


M&A業界は近年、異業種からの転職希望者の間で高い注目を集めています。背景には、社会的・経済的なトレンドが大きく関係しています。ただ単に「年収が高いから」という理由だけでなく、「自分のキャリアを次のステージへ引き上げたい」「社会に大きな影響を与える仕事がしたい」といった志向を持つプロフェッショナルにとって、M&A業界はまさに魅力的な選択肢となっているのです。
M&A市場は、少子高齢化や後継者不足の影響で年々拡大しています。特に中小企業の事業承継需要は急増しており、M&Aは企業存続の手段として定着しつつあります。実際に中小企業庁の調査によれば、今後10年以内に約127万社が後継者不在により廃業の危機に直面すると予測されています。
一方で、業界内では慢性的な人材不足が課題となっています。即戦力となる経験者は限られており、異業種出身でもポテンシャルのある人材に門戸が開かれているのが現状です。つまり、未経験であっても、一定のスキルと意欲があれば十分に勝機があるということです。
M&Aにおいての「即戦力」は、必ずしもM&A実務の経験を意味するものではありません。むしろ、クライアントとの信頼関係を築く力、ロジカルに物事を整理し提案する力、そして粘り強く案件を前に進める推進力など、どの業界でも培える汎用性の高いビジネススキルが重視されます。
特に銀行や証券、コンサルティング業界で磨かれた以下のようなスキルは、M&A業界でも高く評価されます。
これらは、クライアント企業との面談やスキームの提案、デューデリジェンス対応など、M&Aの現場で直結して活かせる能力です。

M&A業界では、銀行・証券・コンサルティングファーム出身者の活躍が目立ちます。なぜ、これらの業界からの転職者がM&Aで成果を上げやすいのでしょうか。それは、業務の本質的な部分で強い共通点があるからです。
まず大きなポイントは、M&A業務とこれら3業界の実務との間に強いスキル的親和性があることです。
たとえば銀行員は、法人営業や融資審査を通じて企業の財務状況を的確に把握する力を持っています。証券会社の営業職やリサーチ職も、企業の成長性や市場評価を読む力に長けています。コンサルタントは、経営課題を深堀りし、仮説を立てて提案を行うスキルを日常的に磨いています。
これらはすべて、M&Aの現場で欠かせない以下のような業務と直結します。
特に、ファイナンスや事業戦略に強みを持つ人材は、M&Aアドバイザーとしての即戦力になり得ます。
M&Aは、高額かつ企業の存続に関わる重大な意思決定です。クライアントが信頼できるパートナーを選ぶ際、単なる数字の知識よりも、丁寧なヒアリングや本質的な提案力を重視します。
銀行・証券・コンサル出身者は、日頃から経営者や役員クラスとのコミュニケーションを経験しているケースが多く、ビジネスの要点を短時間で把握し、信頼を築く能力に優れています。
M&Aアドバイザーに求められるのは、相手企業の将来を見据え、最適な解決策を共に考え抜くスタンスです。この点で、金融やコンサル経験者は極めて高い適応力を持っています。
さらに、M&Aでは「必ず案件を成約に導く」という強いマインドセットが不可欠です。途中で交渉が破談になるケースも多く、粘り強さとリスク管理のバランス感覚が問われます。
銀行の融資営業や証券のディール担当、コンサルのプロジェクトマネージャーなどは、成果への執着心とスピード感をもってプロジェクトを推進する文化に慣れており、この“成約主義”の世界にも自然にフィットするのです。
銀行、証券、コンサルティングといった業界からM&A業界へ転職する際、同じ金融・経営分野での知見を持っているとはいえ、業界特有の慣習やスキルへの理解が不可欠です。ここでは、異業種からM&A業界への転職を成功させるためのステップを、自然な流れで解説していきます。
まず重要なのは、M&A業界の全体像と、アドバイザーとして求められる役割について正確に理解することです。一般的に、M&Aと聞くと、大企業同士の買収劇やクロスボーダー取引といった派手な印象を持つかもしれません。しかし、実際の現場の多くは中小企業の事業承継に関する案件であり、きめ細やかなコミュニケーションや地道な調整業務が求められます。
また、アドバイザーの仕事は、単に買い手と売り手をマッチングすることにとどまりません。経営者の想いを汲み取り、財務・法務・税務といった多角的な視点で最適なスキームを提案し、成約に導く伴走者となることが期待されます。このようなM&Aの実務に触れるには、転職エージェントやM&A専門メディアの情報、セミナー参加、または現役アドバイザーの話を直接聞くことが効果的です。
M&Aアドバイザーとしての実力をつけるためには、財務諸表の読み解きや企業価値評価、デューデリジェンスの概要など、専門的な知識が必須です。これらは実務経験の中で徐々に身につく面もありますが、転職の準備段階から意識的に学んでおくことで、入社後の吸収スピードが格段に変わります。
たとえば、会計の基礎を知りたい場合は『財務会計講義』のような実務家向けのテキストが有用です。また、企業価値評価に関しては『バリュエーション』のような専門書を活用することで、DCF法やマルチプル比較のロジックを深く理解することができます。さらに、法務の観点では、M&A契約書に含まれる条項や表明保証、クロージングまでのプロセスについて学んでおくと、実務に入ってからの理解がスムーズです。
自己学習に加えて、実務者が講師を務めるスクールやオンライン講座も選択肢に入ります。資格取得にこだわるよりも、実践に即した学びを優先するのが効果的です。
転職活動の面接では、これまでのキャリアをどのようにM&A業務に活かせるかを論理的に伝える力が問われます。たとえば、銀行で法人営業をしていた方であれば、決算書を読み解いて経営課題を整理し、適切な融資提案を行ってきた経験をベースに、クライアントとの信頼関係構築や企業理解の深さを強みとして語ることができます。
コンサルタントであれば、複雑な課題に対して仮説を立て、関係者を巻き込みながら課題解決に導いたプロジェクトマネジメント経験を、M&Aのプロセス設計や交渉力に置き換えてアピールできます。重要なのは、「なぜM&A業界を志望するのか」という志望動機を明確にした上で、自分の経験とM&Aの仕事内容を丁寧に結びつけて説明することです。
多くの人は、「未経験だから無理では」と感じがちですが、経験そのものではなく、それをどうM&Aの業務に転用できるかを説明できる人こそが、企業側からも期待される存在となります。
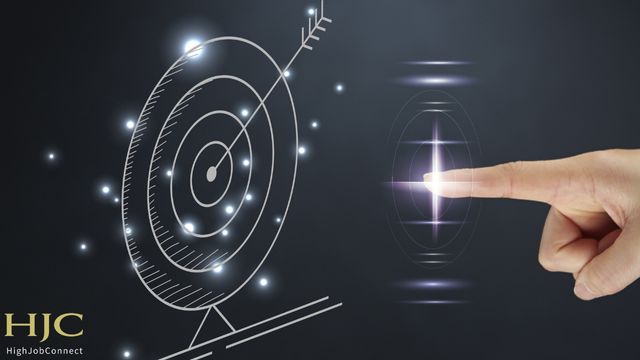
M&A業界は専門性が高く、経験者が有利だという印象を持たれがちですが、実際には未経験からでも活躍している人は数多く存在します。彼らにはいくつかの共通する資質や行動パターンがあります。ここでは、その特徴を文章で丁寧に描写していきます。
未経験であっても活躍している人の最大の特徴は、圧倒的な成長意欲です。与えられた業務だけをこなすのではなく、自分で課題を見つけ、自ら学び続ける姿勢が求められます。たとえば、分からない専門用語を放置せず、調べてメモに残す、日々の案件を通じて得た気づきを整理し、週単位で自己レビューを行うなど、自主的な学びを日常的に積み重ねている人は、短期間で目覚ましい成長を遂げる傾向があります。
また、M&Aの現場では、予測不能な事態や複雑な交渉に対応する柔軟性も重要です。そのため、上司やチームからのフィードバックを素直に受け止め、改善に活かす素直さと粘り強さも活躍するための土台となります。
M&Aアドバイザーは、経営者、税理士、弁護士、買い手企業の担当者など、多様なステークホルダーと関わります。そのため、単に話す・聞くといったスキルだけでなく、「相手の立場や状況を想像しながら話す力」が非常に重要です。
たとえば、オーナー経営者にとっては、会社を売却することは人生の大きな節目です。そのような場面で信頼を得るには、表面的な話ではなく、相手の背景や想いに深く共感しながら会話を進める力が問われます。経験が浅くとも、誠実さや丁寧な対応、相手への敬意をもった振る舞いが、信頼構築の礎となるのです。
M&Aのプロセスでは、複数の選択肢から最適なスキームを設計し、売り手・買い手双方に納得してもらう必要があります。その際に必要となるのが、「課題の本質をつかみ、構造的に整理して伝える力」です。
たとえば、「なぜこの案件はなかなか前に進まないのか」「何が買い手企業にとって懸念材料なのか」といった点を掘り下げ、仮説を立てながら対応策を考える能力が、実務の現場では何よりも重要です。未経験者でも、普段の業務に対して「なぜ?」「どうすれば?」を繰り返す習慣を持つことで、このような思考力は着実に磨かれていきます。
未経験からM&A業界への転職を目指すにあたり、事前の準備は非常に重要です。単に求人に応募するのではなく、自分のこれまでのキャリアや強みがM&Aの現場でどう活かせるかを言語化できるかどうかが、選考通過の分岐点になります。
M&A業界では、即戦力となる知識や経験よりも、自身のこれまでのキャリアの中で身につけたスキルを、M&Aの仕事にどのように活かすかを語れる人材が求められています。
たとえば、銀行で法人営業を経験していた場合には、企業の財務内容を把握する力や、経営者との対話を通じて信頼関係を構築する力が大きな武器になります。また、商社などで複数の関係者と調整しながら案件を進めてきた経験は、M&Aにおける利害関係者間の調整やクロージングプロセスに通じるものがあります。証券会社やコンサルティング会社での資料作成や提案経験も、M&Aのスキーム設計や、経営者への提案資料作成の場面で非常に重宝されるでしょう。
重要なのは、業種を問わず、相手の立場に立って物事を考える視点や、数字に基づいて説得力のあるストーリーを組み立てる力が、どのようにM&Aの場面で発揮できるかを自分の言葉で説明できるかどうかです。
未経験者であっても、業界への理解があるかどうかは、面接時の印象を大きく左右します。面接官は、応募者の言葉の端々から業界研究の深さを見ています。
まず、M&Aがどのような目的で行われるかを理解することが必要です。たとえば、後継者不在を背景にした事業承継型のM&Aと、成長戦略としての買収・統合では、売り手企業の課題や買い手の期待がまったく異なります。また、株式譲渡と事業譲渡の違いや、それぞれのメリット・デメリットも基本知識として把握しておくべきです。
次に、M&Aのプロセス全体についても把握しておくことが望ましいです。初期の案件開拓からマッチング、条件交渉、最終契約、クロージングまでの一連の流れを理解することで、入社後に自分がどのような役割を担うのかをイメージしやすくなります。
さらに、仲介会社とFA(ファイナンシャル・アドバイザー)との違いも理解しておくと、面接での発言に深みが生まれます。報酬体系や関与の仕方が異なることにより、業務内容や難易度にも違いが生じるため、自分が目指すキャリアに照らし合わせて適切な選択ができるようになります。
業界の最新情報を得るためには、日経新聞の企業報道や、M&A専門のオンラインメディアを定期的にチェックする習慣も役立ちます。表面的な知識ではなく、実例に基づいた理解を持つことが、面接の場でも説得力を持たせるポイントになります。
M&A業界での入社後は、スピード感のある実務と高度な判断が求められる場面に直面することになります。未経験であっても、早期に成果を上げて活躍する人には共通する特徴があります。
M&A業界の仕事には、明確な正解がないケースが多々あります。だからこそ、先輩や上司の指摘を素直に受け入れ、柔軟に対応できる姿勢が何よりも重要です。また、わからないことを放置せず、自ら調べ、理解しようとする学習姿勢も欠かせません。
たとえば、財務三表の読み解きやバリュエーションの考え方など、専門性の高い知識が必要な場面では、現場の先輩に聞きながらも、自分なりに本を読み直したり、外部セミナーに参加するなど、自発的に知識を補完していく力が大きな差を生みます。
M&Aアドバイザーにとって、経営者との信頼関係は何よりも重要です。その信頼を得るためには、単に情報を伝えるのではなく、相手の立場や事情を汲み取ったうえで、どうすれば最も納得感のある提案ができるかを考える力が求められます。
たとえば、ある経営者が「できれば地元の会社に譲渡したい」と話していたとします。その言葉の背景には、従業員の雇用継続や地域とのつながりを重視したいという想いがあるかもしれません。そうした想いを丁寧にすくい取り、それに沿った提案ができる人材こそ、顧客からの信頼を獲得できます。
また、社内の関係者とのやりとりでも同様に、他部署の視点を尊重したコミュニケーションが求められます。バックオフィスや法務、財務チームと円滑に連携し、プロジェクト全体を前に進める推進力が重要になります。
M&Aは契約ビジネスであり、1つの数字や言い回しの違いが大きな誤解やトラブルにつながる可能性があります。たとえば、企業概要書(IM:Information Memorandum)の作成時に、数字のミスがあると、買い手企業の信頼を失うだけでなく、売却金額の交渉にも影響を及ぼしかねません。
そのため、資料作成やデータの入力など、表に出ない細かな作業も一切の妥協を許さない姿勢が求められます。高い成約率を誇るアドバイザーは、地味な作業を誰よりも丁寧にこなす傾向にあります。大きな成果の裏には、地道な積み重ねがあるという点を忘れてはなりません。
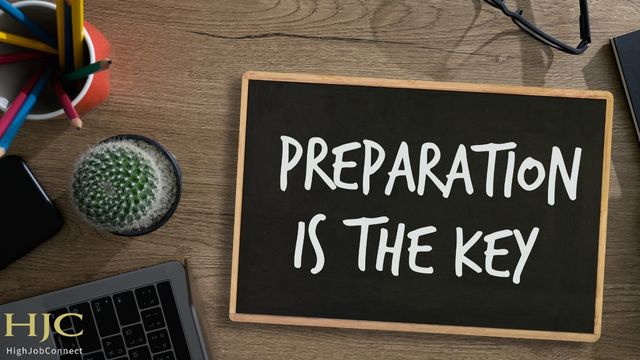
M&A業界は専門性が高く、スピードと精度を求められる世界です。とくに銀行・証券・コンサルといった他業界から転職する場合、即戦力としての期待も大きくなりがちです。しかしその一方で、未経験領域に戸惑うことや、これまでの経験を一度リセットしなければならない場面も少なくありません。
そんななかで活躍する人には、共通するいくつかの特徴があります。まずは、M&A独自の知識とスキルを貪欲に吸収しようとする姿勢。次に、経営者の意思決定に寄り添える共感力や、物事を俯瞰しながら最適解を導くロジカルな思考力。そして、社内外との信頼関係を築き、地道な努力を積み重ねられる粘り強さです。
「未経験だから」と引け目を感じる必要はありません。実際に、銀行やコンサルから転職して短期間で成果を出している人も多く存在します。むしろ異業種で培った視点や価値観は、M&A業務のなかで強力な武器になることすらあります。
最後に、これからM&A業界を目指す方にとって大切なのは、「今の自分にできる準備を、徹底してやりきる」ことです。業界研究、基礎知識の習得、ロジカルシンキングの強化、そして何より現場のリアルを理解する姿勢。それらの努力が、確かな自信と成長の土台になります。