



M&A(Mergers and Acquisitions)は「企業価値」を見極め、譲渡企業と譲受企業の双方にとって最適な着地点を導き出す、極めて定量性の高い業務です。ゆえに、M&Aに携わるアドバイザーやコンサルタントは、数字を読み解き、活用する力が欠かせません。
多くの業界でも財務知識は武器となりますが、M&A業界では“ベーススキル”として求められます。では、なぜそこまで重要視されるのか、2つの観点から紐解いていきましょう。
M&Aの現場では、譲渡希望のオーナーに対して「御社の企業価値は◯億円程度」「この成長率なら今が売り時です」といった提案を行います。ここで感覚的な説明や曖昧な表現では、オーナーの信頼を得ることはできません。
求められるのは、ファクト(財務)に基づいた定量的な示唆と判断です。たとえば、売上・営業利益・EBITDA(利払い・税金・減価償却前利益)などの財務指標をベースに、以下のような比較・分析が日常的に行われます。
こうした分析力と論理的なプレゼン能力の双方が、クライアントからの信頼につながります。
多くの転職希望者が誤解しているのは、「簿記3級程度でなんとかなる」と思い込んでしまうことです。実際のM&A現場では、財務三表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)を単に読めるだけでは不十分です。
実務で必要なのは、「数字の裏にある事業実態を読み解く力」です。
たとえば、
こうした数字の“文脈”を読み取り、買収後のリスク・リターンを適切に説明できる力が求められるのです。
M&Aのプロセスでは、さまざまな財務データが活用されます。実務では単に「損益」や「資産規模」を見るだけではなく、企業の将来性やリスク要因を定量的に把握する必要があります。
このセクションでは、M&A実務において頻出の財務指標・データと、それぞれの活用シーンを解説していきます。
まずは基本となる財務三表について確認しましょう。どれも経営の状態を正しく把握するために必須の資料です。
企業が一定期間でどれだけ「稼いだか」を示す書類です。売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益といった利益段階の数字から、事業の収益性や安定性を判断します。
特に注目すべきは「営業利益率」や「経常利益率」です。M&Aの評価において、収益性の高さは企業価値に直結する重要な指標となります。
企業が「どんな資産を持ち、どこから資金を調達しているか」を示します。自己資本比率や流動比率などを分析し、財務健全性を評価します。
たとえば、買収検討時においては、過剰な負債がないか、棚卸資産が過大でないかなど、リスク評価のベースになります。
企業が実際にどれだけのキャッシュを生み出しているかを示す資料です。PLだけを見て黒字企業でも、CFを見ると営業活動でキャッシュが流出しているケースがあります。
M&Aでは、「キャッシュの健全性」=「継続的な経営可能性」の裏付けとして重視されます。
財務三表に加えて、企業価値算定(Valuation)で多用されるのが「EBITDA(イービッタ)」と「マルチプル(倍率)」です。
EBITDAとは、「営業利益+減価償却費」のことを指し、企業の事業収益力をより実態に近い形で把握するために使われます。非上場企業や中小企業でも、評価のスタンダードとなっています。
たとえば、
このEBITDA × マルチプルの算出には、類似企業の財務比較、業界の成長性、案件特性なども考慮され、M&Aアドバイザーの腕の見せどころでもあります。

M&A業界を志すうえで、財務・会計の知識は「前提条件」とも言えるスキルです。ただし、求められるレベルや範囲はポジションや業務内容によって異なります。未経験者がいきなり高度な分析力を求められることは少なく、段階的なスキルの積み上げが重要です。
この章では、M&A転職を成功させるために必要な財務・会計スキルを3つの段階で紹介します。
まずは「貸方」「借方」や「売上」「費用」「資産」「負債」などの基本的な会計構造を理解しましょう。簿記2級の内容をマスターすることで、企業の財務諸表を読み解く力がつきます。
具体的には、次のようなスキルが該当します。
数字を読むだけでなく、「前年と比較してどうか」「他社と比較してどうか」という相対的な視点が重要になります。M&Aの世界では“財務三表をどう読み解くか”が分析力の差を生みます。
財務知識を実務で活かすには、分析力が必要です。ここで必要になるのが「DCF法(割引キャッシュフロー法)」「マルチプル法」「純資産法」などの企業価値評価(バリュエーション)です。
M&Aアドバイザーを目指すなら、以下の知識が求められます。
ROE、ROA、自己資本比率、流動比率、インタレストカバレッジレシオなど、定量評価の指標は多岐にわたります。これらを状況に応じて使い分け、案件ごとに正確なファクトベースを提示することがアドバイザーとしての説得力を高めます。
M&Aの現場では、Excelでの財務モデル作成が日常的に行われます。実務では以下のようなスキルが重宝されます。
M&Aアドバイザーで即戦力を目指すなら、これらのスキルは必須です。
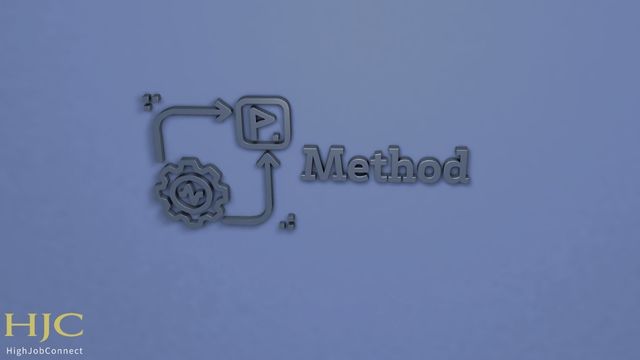
M&A業界を目指すうえで、「何から学べばいいのか分からない」という方は少なくありません。特に未経験からの転職では、限られた時間の中で効率的にスキルを習得する必要があります。この章では、M&A転職に必要な財務・会計スキルを習得するための学習方法について解説します。
まずは「簿記3級→2級→会計実務」へと進めていくのが基本的な流れです。日商簿記検定は市販の教材も豊富で、独学でも学びやすい構成になっています。
簿記2級レベルをマスターすれば、損益計算書(PL)・貸借対照表(BS)・キャッシュフロー計算書(CF)を一通り読めるようになります。
市販の参考書やYouTubeチャンネル、オンライン講座も非常に有用です。以下は人気の高いコンテンツ例です。
| 学習コンテンツ | 特徴 |
|---|---|
| スッキリわかるシリーズ | 簿記初心者向け。図解が多く、理解しやすい |
| CPAラーニング | 会計士受験生にも人気。動画講義の質が高い |
| YouTube「簿記系チャンネル」 | 無料で学べる・視覚的に理解しやすい |
| Udemy | 財務モデリングやExcel分析の講座が充実している |
M&A業界ではExcelでの実務処理能力が非常に重要です。関数操作はもちろん、ピボットテーブル、VLOOKUP、IF関数、INDEX-MATCHの応用まで習得しておきましょう。さらに、簡易的なDCFモデルを自作できるようになると評価が高まります。
理論だけではなく、実際の企業の財務情報を使って分析する「ケーススタディ形式」の学習も効果的です。上場企業のIR資料をダウンロードし、過去の決算書をもとに簡易的な財務分析を行ってみると、実務に近い経験が積めます。
資格は入口にすぎません。特にM&A業界では、実務に耐えるかどうかを重視されます。面接での財務知識チェックや、簡単なケース問題が出されることもあるため、単なる暗記ではなく“理解ベース”で学ぶ必要があります。
ハイジョブやハイジョブコネクトのようなM&A専門の転職支援サービスでは、応募前に自身の知識やスキルレベルについてアドバイスを受けることができます。定期的に模擬面接やスキルシートのレビューを依頼することで、実務力の伸びも可視化され、学習モチベーションの維持にも繋がります。

M&A業界において、財務・会計スキルは単なる「知識」ではなく「武器」です。中途採用の現場では、これらのスキルを活かして即戦力となれるかどうかが、評価を大きく左右します。ここでは、転職活動において財務・会計スキルをどうアピールし、他の応募者と差別化するかを解説します。
応募書類には、「資格名」や「勉強中」だけではなく、どのような業務を想定して学んだか、どの程度まで理解しているかを明記しましょう。
たとえば:
など、スキルと業務への応用をセットで記述するのがポイントです。
未経験者の場合、職歴に直接的な実績がないこともあります。その場合でも、自作の財務分析レポートや、Excelで作成した財務モデルのスクリーンショットなどをポートフォリオとして提示できると、志望度と学習意欲が伝わります。
面接では、「あなたはPL/BS/CFの違いをどう説明しますか?」「企業価値評価で重視する指標は何ですか?」といった質問が想定されます。あくまで“実務の中でどのように使われるか”という視点で語れることが重要です。
たとえば:
など、単なる教科書的な答えにとどまらず、“使いこなす姿勢”を見せると印象が良くなります。
もし過去に苦手だった経験や、学習に苦戦したポイントがある場合も、それをどう乗り越えたかを具体的に語ると信頼感が増します。
M&A業界に特化した転職サービスである「ハイジョブ」「ハイジョブコネクト」では、業界知識豊富なアドバイザーが応募書類の添削や模擬面接を通じて、より実践的な対策をサポートしています。
たとえば:
など、実戦に即した支援が受けられるため、未経験者でも安心して選考に臨めます。
また、スキルセットに応じて「財務知識を重視する求人」「研修制度が整った求人」など、自身に適した求人をマッチングしてくれるため、ミスマッチを防ぐことができます。これは、M&A専門エージェントならではの大きなメリットです。
M&A業界において、財務・会計の知識は転職活動における「評価の土台」ともいえる重要な要素です。とくに未経験からのチャレンジの場合は、資格や実務学習を通じて、自分なりの強みを作る必要があります。
転職活動においては、財務・会計スキルを「自分の言葉で語れるかどうか」が成否を分けます。ハイジョブやハイジョブコネクトといったM&A専門の支援サービスを活用し、しっかりと準備を整えて、キャリアの新たな一歩を踏み出してください。